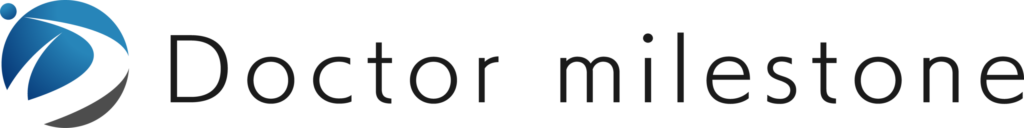日本の医療はどこにいくのか
- 医師数は増加しているものの、都市部への集中が進み、地方やへき地では慢性的な医師不足が続いています。外科や小児科、産科など過酷な当直が伴う診療科には人材が集まりにくく、救急や周産期医療の担い手も不足しています。労働環境は厳しく、特に都市部では当直や夜間対応が多く、週60〜80時間労務が常態化しています。働き方改革が推進されているものの、多くの病院において実質的な労働時間短縮は限定的です。心身の健康面では、過労や責任の重さからバーンアウトや過労自殺のリスクが高く、特に若手・女性医師の離職が増えています。
- 報酬面では、高齢化による医療費増加抑制のなか診療報酬が国により一律で決定されるため、医師の投資や成果に応じた大幅な収入アップが難しく、大学や病院内のポスト競争も激化しています。また、地域医療では、公立病院の統合・廃止が相次ぎ住民の受診機会が減少しています。在宅医療・訪問診療の需要は増加しているものの、人材不足が深刻で、地域包括ケアシステムの再構築が急務といわれています。
- コロナ禍以降、感染症対応で多くの診療科医が再配置され過重労働が増加した一方、オンライン診療の法規制緩和で遠隔診療が普及しましたが、財政難から保険診療はさまざまな規制が設けられるといわれています。そのようななか自由診療も含めた、オンライン診療や開業、医療周辺事業での起業やコンサルティング領域への転身など多様なキャリアを模索する医師が増えています。
医師は医療現場のリーダーである
医師は医療現場においてチーム医療を推進するリーダーです。研修を受けつつ経験を積み重ね、医療技術を身に着けるとともに組織におけるリーダーとして活躍します。医師という役割だけではなくリーダーとしての機能を持った社会人として成長し続けることが期待されています。組織マネジメントについての理解や知識を学習し、医師やスタッフとともに合目的的な活動を行うことが使命です。医師一人で医療を行うことには限界があるなか、医療のみならず社会一般に扱われる課題についても身近なものとして取り扱い、人を動かす、組織を一定の方向に誘導するための活動を行わなければならないと考えています。
医師の職場は多様
医師の職場は多様です。少子高齢化を迎え人口が減少していく日本においては、急性期医療のみならず回復期や慢性期、在宅、プライマリケアの医療のバランスが変化してきています。今後は、高齢者人口ですら減少する日本において、治療用のインプラント開発やAIを活用したデバイス開発、予防医療、健康管理などの領域のみならず、医療に関わる領域はますます増加しています。医療現場においてはデイサーシャリーや美容整形、美容皮膚、肝細胞治療や遺伝子治療など自由診療の幅が広がっていくとともに、食品やサプリメント、化粧品においても医療の高い知識が求められる時代となりました。欧米はもちろんのこと海外の医療ニーズも変化していくなか、ASEAN各国において現地の医療機関において活躍する日本人医師も徐々に増えています。医療の知見を活かし、教育産業や一般企業、法律事務所、コンサルタントとして他の産業においても、高い可能性をもって求められる人材であることが分かります。