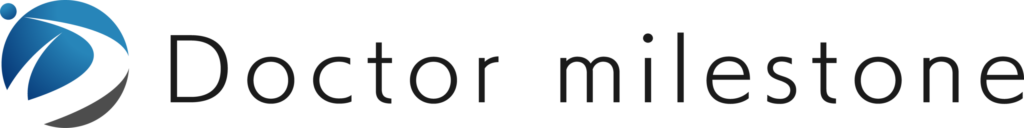組織はリーダーの行ないにより大きく影響を受けます。リーダーの行ないをリーダーシップといいます。リーダーシップが意味をもつのは、フォロワーすなわち部下がリーダーの言ったことを受容れるかどうかに依存します。いくらリーダーが声高に何かを命令したとしてもそれを受容れなければ意味がありません。
直属のリーダーは人事権を持っているので、リーダーには従わなければならないとか、組織では上司のいうことを聞くことが当然であり、命令は絶対だから上司の言うことをきき行動する、ということだけで、果たして命令された側が本当に力を発揮することができるのでしょうか。心から上司の言うことを実行していこう、成果をあげていこうと上司の言うことが受容れるときには、能動的な行動をとることができますが、そうではないときにはどこかで力を抜いてしまうことがあるからです。
自分の考えや思いのなかで、上司から言われなくても仕事を主体的に行う職員であったときに、上司がそれをリーダーシップのなかで支えてくれたり、評価してくれれば、一層やりがいを感じて力を発揮する人がいます。逆に、自分が主体的に良かれと思い、懸命に行動しているのに、上司が水を差すような言動を行うことや、否定してきたときには一気にやる気を失うこともあるかもしれません。
上司からの命令を遵守するのは組織の、そして社会人の常識であったとしても、リーダーシップの在り方により、大きく成果が左右されることを理解する必要があります。
- 経営方針を明らかにし、
- 戦略を明確にしたうえで
- 具体的な行動計画を立案し、
- 役割を決め、
- 行動を促すとともに
- その達成のために支援する。そして
- 信頼し合い、
この人のためだったら働こう、とか多くの職員を守るために仕事をしていこうという思いを持てる関係をつくりあげ、彼らの働くステージを引上げ、やる気にしていかなければなりません。
なお、最近分かってきたことがあります。部下の素直さや柔軟性、属性による障害です。
素直ではない性格や、コミュニケーション能力が低い、なので自分の思いに凝り固まり、言う事を聞けない、あるいは、仕事に向いていない者に対しては教科書通りにはいきません。ここまで書いて、矛盾するようですが、リーダーも人間です。どうしても感性の合う者に、自分の考えに沿って行動してくれる者に気持ちが偏ることは仕方ないと思うし、それが現実なのでしょう。何度説明しても理解してもらえない状況を続けることには限界があります。リーダーは聖人ではなく、ストレスを乗り越えられないこともあるからです。もちろん自分の印象が完全に正しいわけではないので、他人の当該部下に関する意見も聞いて判断するとして、ここで書いた者への対応は骨が折れます。
なお、実務上は全員が期待通りに同じ方向をみれないことをここでも確認しなければなりません。本人に自覚を促し、指導をしつつ、ということになりますが、変われる者から変わってもらうということしかありません。当たり前のことですが。もちろん上司だけではなく組織の風土や文化をあるべきものとしていくことも大事です。常にトップマネジメントは組織の目的を明確にして経営方針、戦略、行動計画、役割付与、支援といったながれを組織全体に構築するとともに、それぞれの部署のリーダーが求められる行動をとれるようガバナンスを行う必要があります。管理会計を活用し常に組織運営を可視化したうえで成果を挙げて行くのです。
いずれにしても、ものごとは教科書のようにいかないことも念頭におき、しかしあるべき形を求めつつ、マネジメントを行う必要があります。ということを前提として、リーダーは、リーダーシップの良し悪しは組織の盛衰に直結することを片時も忘れてはなりません。難しいことですが、リーダーとなる者はその方向に進むことでしか、厳しい環境を乗り越えられないと理解しなければなりません。