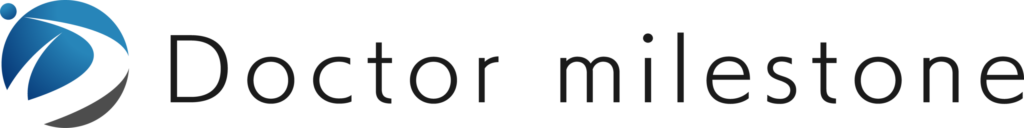どのような業種でも組織マネジメントが必要です。マネジメントというととても大きな概念ですが、組織マネジメントの基本は皆同じです。組織目的を達成するために経営層は、どのように組織を運営していくのかを常に考え行動します。
組織におけるマネジメントは多様ですが、概括的には、ビジネスモデルの創造、マーケティングや戦略立案、事業計画立案、アクションプランの設定を行い、経営資源であるヒト、時間、情報、モノ、カネをどのように活用し成果を挙げて行くのかが大きなポイントになります。
現場においては、それぞれの事業遂行に必要な業務フローがあり、それらの円滑な運営と成果獲得を行わなければなりません。人が多くなれば、または部門が多数できあがれば、それぞれの部門が円滑に機能するよう、適切なシステムや業務フロー管理や人をコントロールする一定のマネジメントが行われることになります。
個々人でいえば、求められるスキルを身に着けることや、それ以前に組織目的に対して正しく行動することができること、さらには人としてどうあるべきかというところまで、取り上げられることもあります。時間管理すなわち、一定の時間のなかでどのように多数ある業務を質を担保しながら、そして部下や上司、仲間と協力しながらこなしていくのか、といったことまで個人のマネジメントの対象となります。タイムマネジメントが必要となります。
そして成果を定量化することで可視化を進めることも、マネジメントの重要なポイントです。業務の可視化を行うっことで、当該組織が担う業務をすべてガラス張りとして、課題を発見しやすくします。もちろん可視化しても、その分析や課題の発見、それらを解決するための解決策が認識できなければまったく意味がありません。数字だけをみて、あるいは数字を出すことが目的化している病院は数多くあります。毎月、とてつもないデータをとりながら、それをマネジメントに活かしていない組織がどれだけあるのか、計り知れないものがあります。
管理会計が導入されることは病院組織において必須であり、そのことにより多くの問題解決や生産性向上に成果をあげることができるようになります。もちろん、定量化は管理会計だけの領域ではなく、さまざまな指標をチェックすることにより医療の質を向上させることにも貢献します。それらにより生産性が向上しコスト削減が行われ、通じて利益に貢献します。
たとえば、救急車で搬送された患者がCTをとるまでの時間や、褥瘡の発生率や治癒率、尿留置ドレーンを外すまでの期間といったことが測定され、どれだけその結果を質の改善につなげることができるのかといったことが議論されています。
物事をすべて定量化することで日常的な行動すべてを指標化し、先行指標を設定することで実績指標と比較して、何が不足して目標に到達しなかったのかをチェックすることが徐々に一般化してきています。医療そのものが科学を基礎としているのに対し、職員の行動自体も科学される状況がここにあります。できるだけ組織の行動をつかみ、目標と照らし合わせて実績を目標値に近づけるために何をすればよいのかを検討することこそが、病院トップや職員に求められるこれからのマネジメントであるということができます。
ここで、病院のマネジメントの対象となる組織(マネジメント領域)について説明します。病院には
- 医局、
- 看護部、
- 診療支援部、
- 事務部
の4つの組織があります。それぞれの組織は医局であれば診療科があり、看護は病棟やオペ室、外来等、そして事務部であれば医事、連携室、企画等の部署に区分されます。なお、病院では部門が縦割りのため、さまざまな部署間での調整が必要になるため、部署間の調整も必要になりますし、病院には急性期(DPCや出来高)、回復期、地域包括、療養病床、精神病床等多くの業態があり、業態により診療報酬体系や提供すべき医療が異なるため業態固有のマネジメントも必要です。
結果、マネジメントの対象は、
- 病院全体組織、
- 業態固有
- 部門、
- 部署、
- 部署間、
の5つのマネジメント領域に区分することができます。
それぞれが最もうまく成果をあげられるように仕向けていくこと、さらには職員の力を最大限引き出すための活動が病院マネジメントの目的であり、医療をもってより社会貢献できる対象とすることができるようになると考えています。
従来の医療そのもののフローを管理することだけではなく、組織や人が最大限のポテンシャルを発揮することができるよう誘導するためのマネジメントをどれだけ的確かつ適切に行うことができるのかどうかが、どの業態の医療においても不可欠であるということを十分に認識する必要あがりますし、できていないところを発見し、できるだけ早期に体系的な修正行動をとらなければなりません。
機能分化と平均在院日数短縮による病院病床の削減が医療制度改革の柱の一つとして推進されているなか、最近では働き方改革の視点も加わり、個々の病院は、組織を維持したうえで自院の社会的責任を全うすることがとても難しい時代を迎えています。自院の地域における役割や進むべき方向を明確にしたうえで、ここで示したマネジメントの充実を行うことが病院生残りのための必須条件であると考えています。