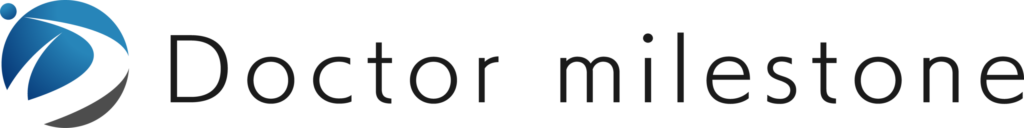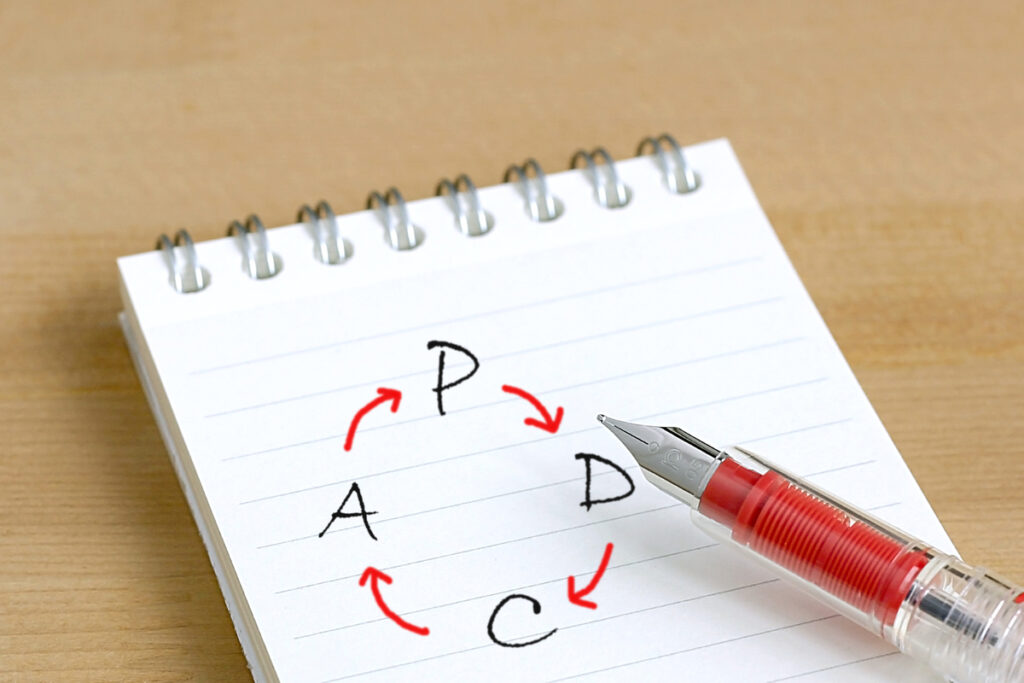
医師のカルテはSOAP(ソープ)と呼ばれる記載の形式になっています。これは問題指向型診療録(POMR=Problem Oriented Medical Record)の一つです。問題志向型医療(POS=Problem Oriented System)の考え方によって得られたデータを内容ごとに分類・整理した上で、S(Subject)、O(Object)、A(Assessment)、P(Plan)の4つの項目に分けて考える分析手法です。
患者の主訴(訴え)や状況・病歴をみて、診察や検査を行いデータを集め、評価します。その結果治療方針を決め治療に入る、という医療活動を記録するのです(看護師の記録も経時[時間軸で誰が、いつ、誰が、どうなったかを記録]やフォーカスチャ―ティング[焦点を絞った経過を系統的に書く]記録方式のほかにSOAPの形式になっているものがあります)。これは患者の治療の記録であり、治療を円滑に行うための考え方です。
私は20年以上前、病院で看護とともに看護記録についてSOAPの仕組みづくりをしているとき、職員の教育体系構築の支援も行っていました。ふと気づいたのは、患者の治療に使うSOAPの考え方は、職員の教育にも使えるのではないかということでした。なんで、職員の治療をするのにカルテがないの?という思いがそこにありました。
当時職務基準やマニュアルも作成しており、教育の立系をつくっていましたが、どうも今一歩日々のOJTの記録方法が確立されていないこと、プリセプティング(プリセプターシップ[プリセプター制度]で、新人[プリセプティー]を先輩[プリセプター]が現場で指導する「現場教育訓練」[OJT]をすること)のときのように、チェックシートにいろいろ記載するだけでは、新人以外の看護師には通用しないと考えたのです。
病棟では、日々の看護プロセス(観察、診断、計画、実施、記録、退院要約)のながれ以外に、山のように看護業務があり、仕事の姿勢や態度を情意考課、能力を職務基準、そして業績を個々人の目標管理やBSCで管理したとしても、統括してそれらを記録しておく媒体がなかったのです。なので、職員の教育カルテを開発しました。
ここではフォームを表示できませんが、「教育カルテ」は、以下の手順で作成します。
- 本人の氏名、作成日を記入する
- 職務基準やマニュアル等に照らし合わせ本人の課題を列挙、本人の考えや意識を評価しながら課題選択
- 優先的に修正すべき問題を選択する
- 選択した習得目標やスキルアップの課題を記入する
- 現状のレベルを確定する
- 目標レベルを決定する
- 期日を決定する
- 教育担当者を決め、サインをしてもらう
- 教育を行う
- 到達レベルを記入する
- 到達した日を記入し、コメントを記載しサインをする
- 次の用紙を用意してレベル未達及び新規課題を抽出する
上記を使い、OJTを開始したのです。
結果として、
- 教育の可視化ができた(本人の問題、そして何を教育したのかを可視化できる)。
- 相互確認ができた(教育カルテを各部署でファイルしておくことで、誰でも、職場内スタッフの課題を理解することができる)。
- 相互教育(教育担当者以外でも課題を相互にみることが可能であり、自分の得意な分野についてのアドバイスができる)→これは恥ずかしいから止めて欲しいとの意見も多くあります。
- 教育側の教育巧拙が確認できる(教育担当者は教えることでスキルもあがるし、また教育の巧拙を確認できるため教育担当者となった職員のスキルも向上する)。
- 振り返り 本人が振り返りを行える(できなかったことができるようになったポイントを確認できる)→読者は「2年前に自分は、何ができず、今はできるようになった」ことが分かりますか?多分半年前のことも覚えていないことがあると思います。教育カルテがあると、組織も振り返りができるので、客観的な評価にも使えるなど結構役に立ちます。
- 自信が醸成される(できなかったことができるようになった用紙の分だけ成長したことが把握できるので、本人に自信が生まれる)
という効果を得ることができました。
今回はこの程度にしておきますが、教育カルテを管理することで上長も部下も常に教育の課題を掌握できるし、期日を決めた教育が行われることも含め、前回のブログで紹介した一人ひとりに光を当てたOJTが確実にできるようになります(いま教育カルテのweb化を行なっています)。教育カルテは、教育の計画、実施、チェック、修正行動を誘導するので教育のPDCAを実現するツールでもあります。
現在、教育カルテは、さまざまな病院で使われています。もちろん、考え方は普遍的なので、どの業種でも活用できますし、使うと便利です。厳しい経済環境を迎え一般の企業においても、生産性向上のための教育が持て囃されていますが、本当に必要なのは、集合教育ではなく職場内教育です。
OJTのためには、教育カルテのweb化やアプリでの活用が有効で、早期に科学的な根拠をもって、これらの構築を行うことが必要です。職務基準やマニュアルがない会社であっても、上司と部下ができないことを話し合い、本人の意見を取り入れつつ、組織の要請に応えるかたちで記録を残しながらOJTを行うと、見違えるように成果がでます。OJTにおいては間違いなく教育カルテを導入する事が有益であると考えています。