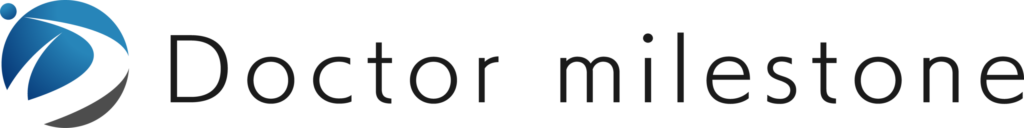計画性とは、目標を達成するために、事前に必要な手順やスケジュールを立て、着実に実行する能力をいいます。計画性があるとないときでは目標達成の質や速度が異なることを誰もが理解しています。つまり、計画性があることのほうが、ないときより物事をうまく進められることを皆が知っているのです。
しかし、計画がなくてもその場その場の課題をクリヤーしていけば一定のところまで到達できるという意見も正しく、目の前のことを先ずは懸命にこなしていくことで成長できることも否定できません。
とはいうものの、比較的後で気づくことですが人生は短く、時間をうまく使うことが人生にとって有効だという考え方に立てば、計画性を身につけた生き方が優位性を以て受け入れられると考えます。
さて、私は三日坊主のタイプです。計画を立ててもすぐに挫折して、当初決めた計画を最後までやり通せないことが多くあります。細切れの計画を随時達成しながら、積み木のように何となく譲歩されたゴールに飛び込む、ような人生を歩んできました。なので、計画性を発揮するためにはどうすれば良いのかを今更ながらに意識しています。以下列挙します。
はじめに、計画性を発揮するためにが達成すべき「目標」があることが前提になります。当たり前ですが目標がなければ計画性も必要なく、やりたいことがなくて日々を過ごしていることも特に問題はありません。計画性を語るときには短期、中期、長期の目標を待ち生きているかどうかが問われます。
なお、目標があってもその目標がすぐに達成できるものであれば計画性はさほど重要ではないかもしれません。あっという間に達成できる目標には、例えば段取りは求められても高い計画性は影響しないからです。ここでの議論において目標は計画しないと達成できないレベルに置く必要があります。
また、目標があっても具体的な達成のための手順や方法が曖昧であればいくら頑張っても目標に到達しないかもしれません。自分は何を達成したいのかどこにいきたいのか到達点を決め、現状を認識した上で、到達点と現状のギャップを埋めるための解決策を徹底的に検討し計画に結びつけます。適切なKPIを設定しPDCAで管理していきます。的外れなやり方や行動では成果を得られません。
もちろんPDCAを廻していくなかで、当初立てた計画に課題があれば途中で修正し、再度修正した計画(仮説)に基づき行動(検証)し、さらに課題があれば次の仮説を立てて検証活動を行う、そして、というように当初の計画は常に環境適合できるよう仮説→検証→仮説→検証という行動を継続していかなければなりません。
さらに、目標達成の手順やスケジュールがあっても目標に執着していなければ目標は達成できません。手順通りに進まないことやスケジュールをこなす意欲が喪失し途中で諦めてしまうことがあるからです。背景にはさまざまな理由があるとしても何が何でも目標を達成するという強い意思がなければ計画性は維持できないのです。
そして極め付けは自分を取りまく有益な環境が計画性を効力あるものにするためのポイントです。目標に向かい努力する自分を鼓舞してくれたり支援してくれる先輩や共に活動してくれる仲間、そして場合によれば家族や自分の健康も目標達成の要件になります。
目標に自分一人で立ち向かわなければならない、他に心配事があり目標達成行動に身が入らない、という状況では目標達成はおぼつきません。周りの誰もが助けてくれて自分がうまく活動できる環境をつくるためには、家族をも含めた良好な人間関係を積極的につくれるよう自らを律することが求められます。
こうして考えると計画性がうまく機能して成果を挙げるためには
- 時間は有限だとの認識
- 目標の存在
- 背伸びしなければ達成できない目標の存在
- 適切な手順や方法
- 目標への執着
- 目標達成のための環境づくりといった要件が必要になりますね。このほか自明の理として
- 目標に関連する知識や知見、経験
が求められるのはいうまでもありません。なお、組織において一定成果を挙げるときにも上記の要件は不可欠です。意外とルーチンの中での目標設定が行われている場合には上記への取組みが脆弱になることがあるからです。
計画性を発揮するための7つの要件に留意しながら、より一層の努力をしなければまずいという結論です。