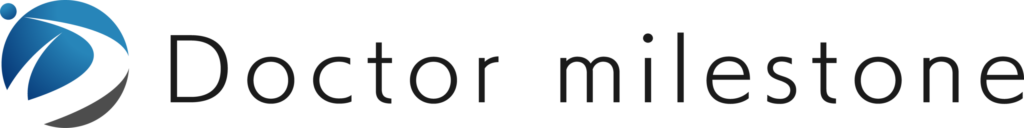物事を円滑に進めるためにはルールが必要です。暗黙のルールもありますが、明示的なルールがあれば、誰でも基本に立ち戻れます。仕事をする上でベースとなるルール記載した規程について説明します。組織が小さいときにはあまり気にはなりませんが、ある程度の規模になったときには、これらがないと、あちらこちらで混乱が起こります。これは俺の仕事ではないですよね、とか、それは私に責任あるんですか?とか、これって誰かに許可必要でしたっけ?のようなことが常に起こるし、君ってこんなこともできないの?とかいうことがあちらこちらで常態になるからです。ルールがあり、周知されていれば、組織がうまく回る可能性はかなり高くなりますよね。
ということで、何処かで必ず役に立つ職務分掌、職務権限、職務基準の3つの規程、ルールを簡単に紹介します。まず、職務分掌は各部署毎の業務(≒仕事)の担当を示す規程です。〇〇部署の業務は、これといった決め事により、当該部署の業務内容が明らかになります。権限規程はそれぞれの業務の権限をきてする規程です。職務分掌により各部署の役割が明確になるとともに、権限規程によりそれらへの権限と責任が明らかになります。
そして職務基準は、職種や職能等級制度における資格ごとに、各業務を課業レベルに分解し、どの資格者がどのレベルまで当該課業を実行できなければならないと決める基準です。
1.職務分掌
職務の分担が明確でないと、その仕事は自部署のものではないというケースが出てきて仕事ができなくなる事態になります。職務分掌が網羅的かつ明確であれば、Aという仕事はA部署の、BはB部署の仕事であると決まり、それぞれの部署が連携しながらある業務ができるようになります。但し、緊急時にAという仕事が発生したときに、A部署のメンバーがいないとある業務は停滞します。いつでも何かあったときに対応できるように、どの部署でもできるようにしておく必要のある仕事もあります。そうはいっても多くの場合には部署内において担当者が決まっているとしても当該担当者が不在のときには別の担当者が業務を担うという決め方が多く、一般的にはよほど規模の小さな組織以外で、部署間をまたいで同じ業務を職務分掌に入れることはありません。
2.権限規程
権限は、
- 起案、
- 審査、
- 承認(実施)、
- 報告
の4つで行使されます。承認の後の実施は、承認を受けた起案部署が行うので、実施権限は起案部署もしくは起案者にあります。
ここで、起案はこれをしたらどうでしょうという提案をすることです。また、審査はそれが業務に必要であるのか、予算内であるのか等をチェックすること、また、承認は実行していいという決裁を行うことをいいます。そして報告は、決裁の結果実行されたことが当初の決裁通りであったことの報告を受ける権限をいいます。これらがルール化されていないと、責任が明らかになりません。なお、権限は実行責任を伴います。やるからには責任とってね、ということですね。
3.職務基準
職種別資格別に職務や課業を明らかにした規程です。職務(仕事)は、いくつかの課業に分かれます。課業とは一人ひとりに与えられた仕事の単位をいいます。例えば発注業務であれば、発注すべきものの確認、発注承認、発注ソフトの立ち上げ及び発注入力、発注後チェックといった仕事に区分されら、といった具合です。場合によれば相見積りの入手、検討、値引き交渉といった仕事も追加されることもあります。これらを活用することで、Aという仕事はA部署のどの職位(役職者=所定の資格者)が(予算の範囲で)どのように仕事を進めていけばよいのかが明らかになります。逆に言えば、この職位の人はこの仕事ができなければならないですよ、という基準になります。資格により所定の課業について、支援すればできる、独りでできる、完全にできる、教えることができるに区分しています。
なお、ここで資格者についてですが、職能等級制度では入職したときに資格が付与され資格が上がる過程で役職が任命される仕組みになっており、ある職位の者には同時にある業務(課業)を行う義務や責任があると決められ、そのルールに基づいて仕事が進むみます。ということで人事評価(考課)や教育のためにも、職務基準が無いと管理が難しくなろことは間違いありません。君は規程上完全にできるレベルじや無いとダメだよね、と言った評価を行い、不足するところを教育の対象とするのです。
如何でしょうか?かなり端折って話しましたが、ここでいう3つのルール、規程や基準が、業務を適切に行うために不可欠です。実務においては、これらすべてを整備しなくても業務は回ることが多く見受けられます。自然に出来上がったルールのなかで組織が運営され、役職による上下関係があれば、それで「事足れり」というケースです。しかし、冒頭説明したように、職務分掌がないため部署毎の業務の境界線が曖昧で、組織で仕事をうまくすすめていけないことや、権限規程がないことにより、組織内における責任が不明確になり、事が進まず権限なく事が進んでしまい、問題が発生することがあります。また、職務基準がないため仕事ができない上司が跋扈したり、評価や教育が上手く進まないため処遇に公平性を欠き、職場に不満がたまることも増えてきます。
組織が一定規模になったときには、生産性を担保する基本中の基本であるこの3つのルールを整備し、ムダのない運営が行われるければなりません。