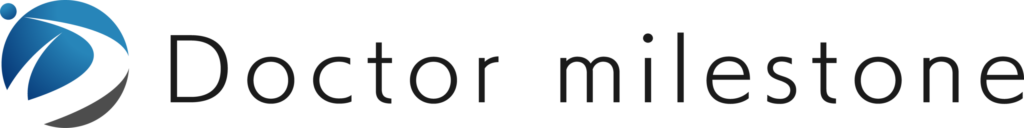今回は比較を考えます。経営学では「比較」が盛んに行われています。馴染みのあるものは以下のものです。
- 競合他社との「比較優位」を持つことで持続的に利益を上げるポーターの「競争戦略」
- 業界内外の「ベスト・プラクティス」と自社の現状を比較して改善点を発見し、業務を最適化する「ベンチマーク」
- 強み、弱み、機会、脅威について企業内部と外部の要因を比較・整理し、戦略立案の基礎とする「SWOT分析」
- 他社と自社は「何が違うか」「何を強みとできるか」という比較を通じて、企業の戦略的資源を特定するリソースベースド・ビュー(RBV)と「コア・コンピタンス」
- 複数のプレイヤーが相互に影響を及ぼす状況で、各プレイヤーが他者の行動と自らの行動を比較・予測して最適戦略を決定する「ゲーム理論」
「自他の比較」によって、自己の強みやポジションを認識し、最適な行動や戦略を導き出すことを目的としていて、「比較」は経営学の核心的な要素の一つです。
ただ、今回のテーマは人を対象としています。人の比較を考えてみたいと思います。
人は一人では生きていません。多くの人々の中で生きる「社会的存在」であり、自分と
- 自分の何かと他者の何か
- 自分の何か
を比べて(比較して)生きています。
組織行動論における「社会的比較理論」のなかで、レオン・フェスティンガーは、人は自己評価のために他者と比較する傾向があり、この比較がモチベーションや満足度、離職意図などに影響を与える、と説明しています。
ただ、自分と他者と比較することで、自分を良い方向に誘導できる可能性はあるものの、逆に慢心したり劣等感を感じたり、やる気を失うなどのデメリットがあります。
そもそも、自分の何かと他者の何かを比べるとき、自分からの他者の見え方は主観的な思いや感情に左右されることがあり曖昧です。他者を知悉していない状況では、他者がどのようにその状況に至ったのかの背景も、他者の絶対的な価値も実は分かっていないからです。他者のすべてを総合的かつ客観的に判断できないとき、必要のない驕りや嫉妬、無駄な不満足をもつことは意味がありません。
自分の何かと他者の何かを比較するときには、自分にとってメリットとなる比較を採用しなければなりません。
他者が自分より優れた点をみつけ、あんな行動を取りたい、あんな風になりたい、あんな成果を挙げたいという前向きな方向で、自分を鼓舞したり目標設定のきっかけにしていきます。もちろんポジティブな思考性のある人は、はなから比較によるデメリットを遮断しており、そうした考えすらもたないことは明らかですが、敢えて言えばこの点の留意が必要ですね。
重要な比較は自分の何かの比較です。私は、
- 自分の過去と現状、
- 自分の現状と未来
という区分をしています。この比較の根底にあるのは自立です。「自分が何をしたいのか、またどのようになりたいのか」というベクトルが前提になります。この2点があれば、これらの目標に向かい、自分はどのように計画し行動しているのかといった評価を行えます。
- 過去決めた方向に進んでいるのか、
- 過去と現状にどのような乖離があり、
- 合目的的な活動が行えた帰結が今なのか、
- 不足したところは何か、
- どのような課題があったのか、
- 解離をなくすためにはどのように行動すればよかったのか
を振り返ることができます。
もちろん、経過のなかで当初予想しなかった環境変化や自分の経験、社会の関係性など変化しており、過去に自分が何をしたかったのか、またどのようになりたいと考えたのか、と現状は異なっている可能性があります。なので、振り返りの後、未来に向けた活動を開始します。
自分の現状を認識したうえで、再度未来の自分を想起し、自分はどうなっていたいのかについて検討します。過去と現状の相違を認識し、そこを踏まえたうえでプランニングを行い、行動を開始するのです。結局ものごとはすべて仮説→検証の繰り返しです。こうなろうなりたいという計画を立て、そのために必要な事項について仮説を立て活動し、その検証を行いながら修正し次に進むというフローを繰り返すことにより、行動が徐々に自分の到達点に収斂していき成果を挙げます。
ところで、自分にしても他者にしても何かを比較する何かの「何か」は何を表すのでしょうか。拙著サクセスキューブで提唱したように、人が成功するための要件は、想い、信念、技術・技能、人間力、コミュニケーション力、達成感の6つです。ここでは詳しくは説明しませんが、人が成功するためにはこれら6要件を順番にあるいは並行して身に着けていかなければなりません。
これらについて自分が求めているものと現状はどうなのかという比較を自分の中で行うときに、その形成に役立つ情報を得るために自分や他者と比較する。自分のこうなりたいという思いはどうなのか、信念に昇華されているのか、必要な技術・技能は身についているのか、人間力は備わってきているのか、コミュニケーションはできているのか、そして何よりも達成感を得られているのか、について自分の時系列の変化を認識するとともに、優れた他者から情報を得て啓発され、未来に向けて能力を高めたり成果を挙げて行けます。
- 「自分が何をしたいのか、またどのようになりたいのか」を常に念頭に、
- 自立して他者との比較、自分の過去や現状、現状と未来の比較を連続的に実施しながら、
- モチベーションを高め、
- 生活していくこと
を自分の成長のための一つの方法として行動していくことが望まれます。