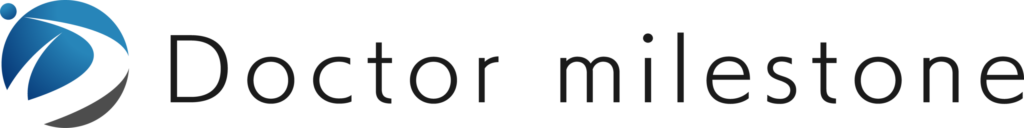人は毎日、起きてから、なにかしらの達成感を抱いて布団に入るまで「こうしよう、いや、ああしよう」と、さまざまな意思決定(なんらかの目標を達成するため、いくつかの選択可能な代替的手段の中から最適なものを選ぶこと)をしながら生活をしています。
なかには習慣となっている行為もあり、朝、何も考えずに顔を洗い歯を磨き、トイレに行き朝をスタートすることはあります。
しかし、何を食べるのかとか、どんな服を着るのかについては、小さな意思決定を行います。そして、自宅を出て歩き、電車に乗り、勤務先に到着して一日のスケジュールを確認し仕事を始めると、意思決定の回数がどんどん増えてきます。
処理の手順を間違えたり、報告のタイミングを遅らせることが後に重大なロスになることもあり、大げさに言えば全知全能を以て決定しなければならないことがたくさんあります。
ミスをした部下の指導、予想できなかったことへの対処、上司への報告、新しい業務への対応、決定会議での発言など、意思決定を繰り返しながら仕事が進みます。
ここで本人が管理職であれば、病院の設備投資や予算達成、突発的に発生するリスクへの対応など、的確な決定ができなければ、組織運営を誤る可能性があります。意思決定を行うにあたっての考え方や、方法について、あるべき基準をもたなければならない理由がここにあります。
- 目的の確認、
- 状況把握(情報収集)、
- 代替案列挙、
- それぞれの代替案の優劣(メリット、デメリット)検討、
- 意思決定
といったプロセスを経る必要があります。
上記を通じて意思決定を行った結果、収益やコスト、周囲にどのような影響があるのか推測し、最適な結果(最適解と言います)を得るためにどのように決定を行うのか判断しなければなりません。
無目的に、到達点も不明ななか、感情で判断したり、熟考せず何かを決めてしまうことは、個人としても組織人としても、とても危険です。とても難しいことではありますが、人として、組織人として何かを決めるとき「どうすれば正しい意思決定を行うことができるのか」を常に念頭に置いて冷静沈着に行動したいと考えています。でも、実際には時間がない選択肢が思い浮かばないといった理由で、思い付きやその場の判断で何かを決定してしまうなど、上記が出来ていないことが多くあります。日頃からあらゆることに目を配り環境変化を理解したうえで、代替可能なABCDといくつもの選択肢を想定する訓練を行い、徐々に精度を深めていくといった流れをつくることが有効です。
熟考する、といったキーワードを日常に取り入れ行動していくことで、従来を超えた成果を挙げることができると考えています。