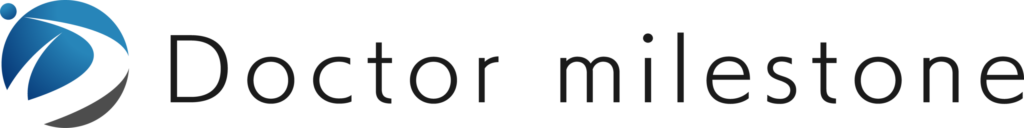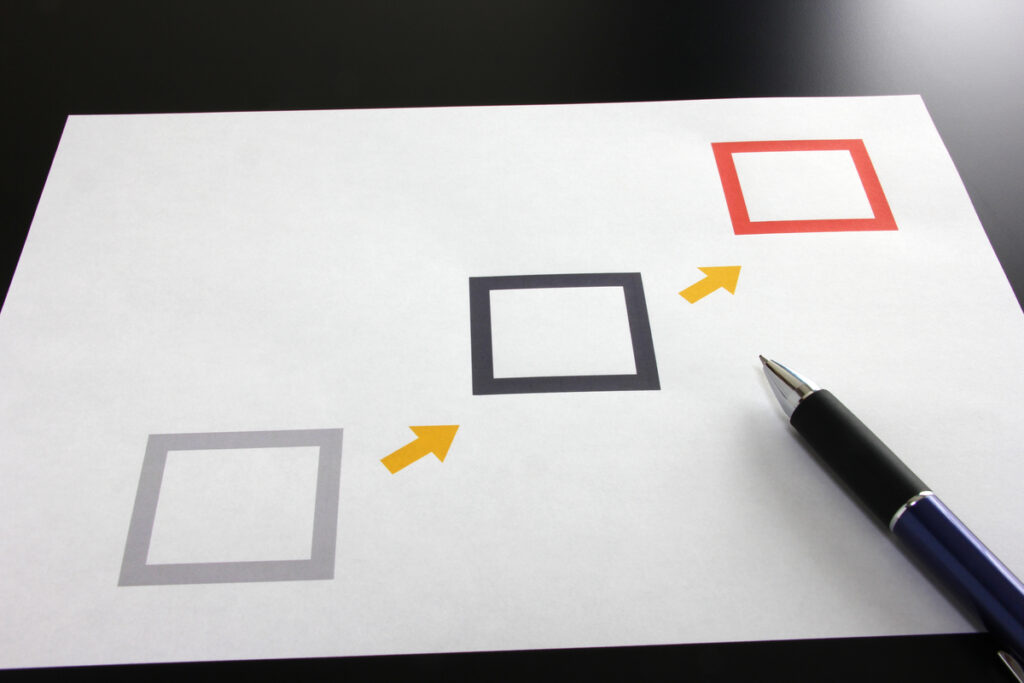
病院において、教育というと、どこかの研修に行くとか、セミナーを聞きに行く、資格をとる、と考える向きがあります。本当にそうでしょうか。教育をどのように行うのかを考えなければなりません。
日々職場で行われている指導は、個々の上司が彼らの知識や経験で行われ、体系化されていないため、教育というよりも必要に迫られて指導している傾向にあり、教育制度に昇華されていない病院が多くあります。実質は教育であるにもかかわらずその場その場で行われているため成果が挙がりづらいものになっています。
教育には
- 職場内教育、
- 集合教育、そして
- 自己啓発
の3つの柱があります。
まず、職場内教育はいうまでもなく、職場で行われる教育です。どのような仕事でも、その組織においてつくられてきた、仕事のうまいやり方やルールがあり、それらを遵守すれば成果をあげることができます。
仕事のナレッジ(知識=ノウハウをも含む)を正しく伝え、深めていくことが職場内教育の役割です。職場内教育で学びきれないナレッジがあれば、組織内部でそれらに長けている人から学ぶ、あるいは組織外部で学習機会を得ます。
職場内教育で使う道具は、
- 職務基準と
- マニュアル、そして
- 教育カルテ
です。
職務基準は職場にあるすべての職務を網羅した表であり、等級や職位に応じて行うべき職務を規定しています。一般的に、ある仕事を「支援すればできる」、「独りでできる」、「完全にできる」、「教えることができる」というレベルで本人の仕事のレベルを評価します。
又マニュアルに記載されている手順、留意点、必要な知識などの項目をも実施できるよう、職員一人ひとりの教育カルテに育成課題を記載し、一つ一つ指導を徹底、一定の期間内にすべてできるように仕上げていきます。
例えば、革新的な病院の看護部ではプリセプティング、卒後研修、ラダーといった道具によりさらに多角度から教育が行われますが、他の部署においても、まず職場内教育の仕組みを確立し、職場における一人ひとりの職員の技術技能の課題を修正し、技術を向上させることが最優先されなければなりません。
教育カルテは、患者にカルテがあり、治療を行うのに、職員の課題解決カルテがないのはおかしいと気付き開発された、職員一人ひとりの教育を行うツールです。不足するところを列挙し教育を行いながら当該不足事項をクリヤーした記録を記載するAカルテと集合研修や外部研修の履歴を記載したBカルテに分かれています。
そして就業教育です。職場内に教える人がいないなどの事情により、教育における不足事項を補足する意味合いでの職場内での集合教育には意味があります。職場内教育→職場内集合教育→職場内教育→外部集合教育…とレベルを上げていくこともできます。
いずれなしても、集合教育は、組織において知識が不足するとき、あるいは新しいナレッジを収集するために実施する教育と捉えることが必要です。職場のうまい仕事のやり方の基本は各職場固有に存在するのであり、はじめから職場の外に青い鳥を追い求めることは的外れだということが分かります。
そして3つ目の教育の柱である自己啓発は、職場内教育や集合教育で得た知識をさらに深めていくときに目標を決めて自分自身で学習する教育です。組織として何等かのかたちで支援する必要のある領域です。
まずは職場内教育が最も優先し、それを充足するために職場内教育、自己啓発と進め、不足するとことを外部研修による教育を行うながれを忘れないようにしたいものです。なお、外部の研修が研修を受けた者だけの財産にならないよう、本人の研修報告と併せ資料をデーターベース化するとともに、検索が容易にできるシステムとするなど、誰でもリスタディできるよう仕組みを作る必要があります。
個々の部署での教育、組織としての教育の在り方を整理して具体化、そして体系化することが医療の質を向上させ生産性を高められる人材育成にとってとても有効であると考えています。