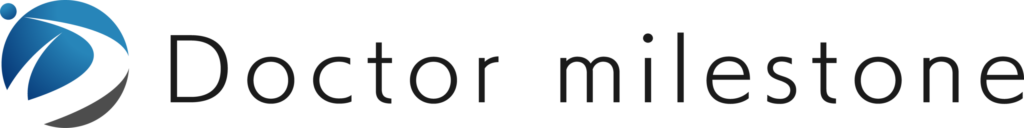報連相という言葉を聞いたことのない社会人はいないと思います。報告、連絡、相談の頭文字をとっています。業務を円滑に行い効率化することが報連相を行う目的です。報連相をすることで、人や組織内の意思疎通がとれ業務効率が上がると言われています。
しかし、実際に「報連相をちゃんとやろう」といわれ、報告、連絡、相談という言葉は理解しつつ、報連相を丸ごと意識して日々上司や部下とコミュニケーションをとっている人は少ないのではないでしょうか。
そもそも、報告をするためには、報告をしなければならないシチュエーションがあり、連絡にも理由は背景があるのが一般的です。また相談をするにも相談をしなければならない状況があるので相談を自然にすると考えています。
報連相を捜し仕事をするのではなく、そうしなければならない理由があるからそうするのであって「何か報告するものはないかな」とか「連絡しなければならないものは何だろう」とか「相談しなければならないんだったら何を相談しよう」ということにはなりません。
すなわち報連相をしよう、ではなく、
- ミッション、ビジョン、バリューをベースとした目標を明確にして結果を必ず検証(報告)し、次に進む仕組みがある、
- 情報共有することが仕事の一環であり自動的に何かを行ったら連絡が行われるルールや文化をつくる。さらに
- 自分で解決できないことを1on1で相談する場がある、
- 自分でできないことは関係部署や関係者に手伝ってもらおう、助けてもらえるという風土ができていたり、
- 上司が意図的に部下の話を聞きながら仕事を行う上司であるといった教育や人事が行われている
ことが必要だという帰結です。
なので、みんな報連相をしようね、という指示がいかにナンセンスであるのかということです。経験上、活気のある組織やチームでは何も言わなくても報連相が自動的かつ的確に行われているし、コミュニケーション不足による仕事の障害や、問題の発生がありません(ありませんというと語弊がありますが、とても少なかったように記憶しています)。
結局、報連相しよう、ではなく、報連相が自動的に行われる組織をつくろう、仕組みをつくろう、文化や風土をつくるための教育を行おう、とすることが適当です。
すべての組織はそのことに気付かなければなりません。
例えば、ほとんどの組織で権限規程が整備されていなくとも取り入れている権限の四行使にあるように、何かの業務を行うときに誰かが「起案」し、上司が「審査」、「承認」して実行された仕事の結果が承認権限を持っている人や機関に「報告」されるという明示的もしくは暗黙のルールがあったり、会議においてはbefore、afterの管理のなかで議事録が残され、それを必要な者が閲覧しフォローする仕組みもあります。これらはどのような属性の組織においても徹底されなければなりません。
また例えば営業部署に日報があり、開発部には日々の工数管理のための記録があり、工場には生産性管理のためのデータがあります。
他の部署も含め、結果としてこれら活動履歴やデータをもとに目標に沿った振り返りが行われ、KPIをベースとしたPDCAサイクルを廻していくことで、自動的に報告、連絡は行われるしPDCAのAので次のPをつくるための相談が行われます。
1on1においても頻度にもよりますが、個人個人のレベルで現状の評価、役割の認識、依頼、実行支援が行われて自動的に報連相が実施されていることも理解されなければなりません。
また、ナレッジマネジメントで言われるように、活気のある組織では暗黙知のやり取りがあり、マニュアルや他の媒体による形式知化が行われ、個人知が組織知化されています。このプロセスでは間違いなく仕組みとして狭義の連絡や相談、業務の効率化に関わる報告が行わています。
少し幅の広い展開になりましたが、こうした活動をしっかり組み立てれば、個々人がそれぞれの思いを達成できる仕事をもちながら日々活動するなかで、組織が自動的に目標やミッションを達成できる環境ができあがります。
そのような状況においては「報連相をしよう」、ではなく「皆で自分のやるべきことをしっかりやって成長し達成感を得ていこう」、というだけで事足りるのです。
なお、組織に仕組みやルール、文化や風土、そして教育システムが整備されていたとしても、稀にそれを遵守できず「君は何で報告しないんだ」とか「それはちゃんと〇〇部署と情報共有しておいてね」とか「そんなこと俺に相談してよ」とかいう個別の指導をすることはあると思います。その場合でも「報連相をしようよ」という一括りでの言いかたにはなりません。
組織管理者は「報連相をしよう」と声高に叫ぶ前に、先ずは自分たちが日々の業務を円滑に行えるガバナンスを行えているかどうかを胸に聞いてみる必要があると考えているのです。