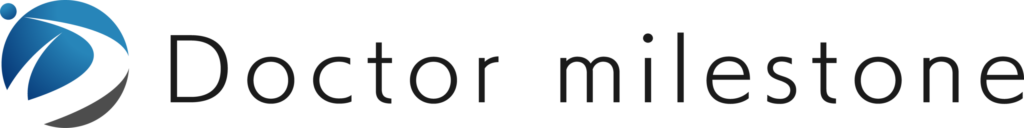日本の医学部教育には医療マネジメント(経営・管理)に関する体系的な講座がほとんど用意されておらず、医師がリーダーシップやマネジメントを担う場面に対応しきれていないのが現状です。しかし、医療の質向上・効率化・持続可能性を目指すうえで、医師が経営知識を身につけることは極めて重要です。
医師がマネジメントを学ぶ意味は、単なる「経営スキルの習得」にとどまらず、医師がマネジメントの知識を習得することで、医療機関全体の運営力が向上し、医療の質の維持・向上や組織全体の持続可能性が強化されると期待できます。いくつかアイテムについて説明します。
1. 医療現場におけるリーダーシップ
医師は診療だけでなく、多職種チーム(看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、事務職員など)を統率する立場に置かれます。チーム医療の重要性がますます高まる現代において、医師には、高い専門性に加えて、組織をまとめ、人を動かす「マネジメント力」が求められています。ここではリーダーシップが必要となります。リーダーシップとは、組織目標の達成に向けて、チームを鼓舞し、方向性を示し、メンバーをまとめていく力のことです。
医師として豊富な経験を持つだけでは、必ずしも優れたリーダーになれるわけではありません。ここで必要なのがリーダーシップ理論や人材マネジメントの理解です。目標管理(MBO)やバランストスコアカード、1on1、フィードバック技法などを活用することで、
- 個々人の能力を引き出し達成感を得る機会を提供する
- チーム全体のモチベーションを高める
- チームのパフォーマンスを上げる
ことができます。
2. 経営的視点の導入
医療機関の経営は保険診療であれば、社会保障制度や診療報酬に強く依存しており、また自由診療においても、安定運営を行うためにはマーケティングや戦略、財務会計・キャッシュフロー等の理解が不可欠です。マネジメントを学んだ医師は、
- 医療機関の収支改善や資金調達
- 医療機器導入の費用対効果分析
- 新規サービスの導入判断
を主体的に担うことができます。
3. 医療資源の最適配分
病床数、医療スタッフのシフト、手術室や検査枠の稼働管理など、医療は「限られた資源のマネジメント」が不可欠です。財務や部門別損益計算、患者別疾病別原価計算や指標管理マネジメントを学ぶことで、
- 診療報酬制度を踏まえた経営判断
- 患者ニーズに応じたベッドコントロール
- 診療科間の人員配置調整
といった意思決定を合理的に行えるようになります。
また、医療機関だけの課題解決ではなく、医師のこれからを考えた時、医師自身のキャリア開発についてもマネジメントを理解することには大きな意味があります。
勤務医に限らず、開業、企業勤務、研究・政策、海外での医療、起業など多様なキャリアを選ぶ医師が増えています。多様なマネジメントを学んでおくことは、医師がどのようなキャリアを選択しようとも、
- 自分のキャリアを主体的に設計する
- また計画したことを戦略的に実行する
- 思い通りの成果を挙げる
ことにつながるなど社会で新しい価値を生み出すための基盤となります。
ここにすなわち、医師がマネジメントを学ぶ意味は、医療の質を高め、医療機関の持続可能性を支え、患者や社会により大きな価値を提供するためであり、同時に自身のキャリアの選択肢を広げるためでもあることが分かります。大げさな理論ではなく、実務に即した手法やフレームワークを理解することで上記をクリヤーすることが可能です。
日本の保険医療は大きく変化してきており、医療機関は厳しい環境のなかで医療を継続していかなければなりません。勤務医として、開業医として、また海外での医療を選択しても、企業のなかで力を発揮するにしても組織マネジメントのスキルを身に着けておくことには大きな意味があるという帰結です。いわんや経営者として医療周辺事業での起業を目指すのであればなおさらです。多くの医師の積極的な取組みが医療にも個人にも、そして社会にとっても有益です。