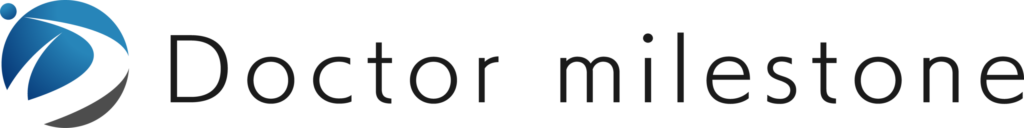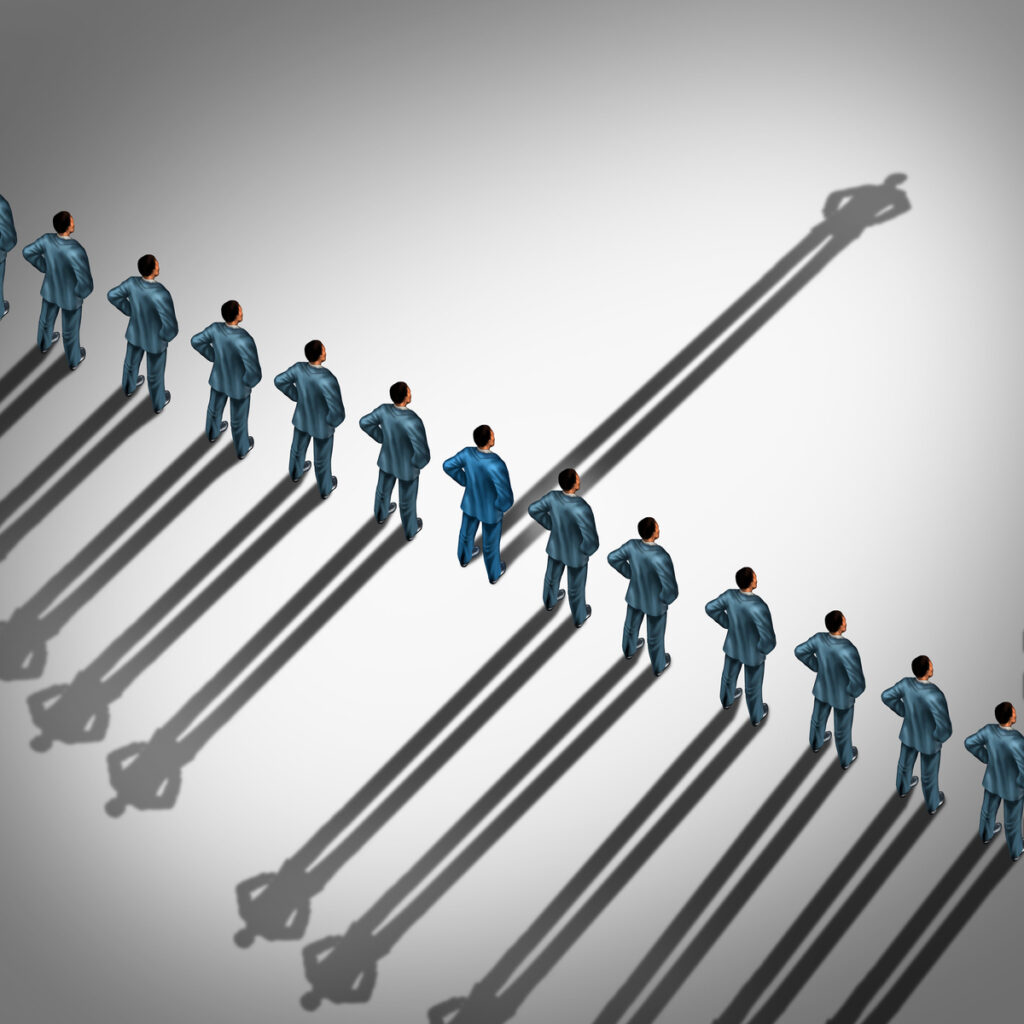
さまざまな組織からの依頼で人事考課制度導入を行うケースが増加してきています。以下は最近の医療機関のレクチャーで使った資料です。
「人の評価は賞与の評価と人事考課に区分できます。人事考課は、
- 情意考課
- 能力考課
- 業績考課
- 日常活動
- 勤怠管理
に区分されます。もう少し詳細に人事考課の項目を説明します。
仕事に対する姿勢や態度、身だしなみや責任感や協調性、部下をもっているレベルであれば教育、患部であれば経営に対する意見具申などが情意考課の対象となります。また、能力考課は職務基準、そしてその背景にあるマニュアル等により技術技能を考課するものです。発揮能力を以てこれを考課することになります。業績考課は年間を通しての賞与2回分の成果を評価します。賞与支給時には業績評価といいますが、人事考課においては業績考課となります。
さらに委員会活動や外部講師、学会での発表、論文投稿といったものを基礎として、日常における活動をすべて加点で考課します。これらはプラス要素として捉えており、積極的な成果を期待するものです。勤怠管理は、遅刻や早退、公休や有休を超えた休暇などについての評価を行います。上記5つをもって人事考課とし、職位のカテゴリーにより割合を異なるかたちで評価することになります。
多くの組織の場合、賞与は一律、給与は年功序列といった形で行われることが一般的ですが、それでは本当に成果を挙げた者に不公平感が生まれ彼らの力を引き出すことができなくなります。個人の活動をつぶさに評価し、処遇に反映しなければなりません。また、上記評価や考課により課題を発見し教育の基礎とするための評価制度を導入することで体系整備を行っていくことになります。
ここでは、賞与や昇給昇格昇進にどのように評価を反映させるのかについてのビジョンを視野にいれておかなければなりません。年齢や職位を分析し、等級や号俸に落とし込み(職能等級制度)、賃金テーブルをつくるとともに、モデル賃金を決定します。このような能力を持つ者は、こんなかたちで昇給、昇格、昇進していきますという形を見せることにより、働く者のモチベーションを上げます。
そして前述のように仕事の姿勢や態度の評価、資格や職位に合った能力の評価、そして設定した目標の達成状況による評価、日常評価や勤怠管理により人事考課、すなわち全体的な評価を行います。目標の達成状況による評価は半期ごとに賞与の対象になるという帰結です。
目標管理制度の評価をどのように行い、部署と個人の業績をどのように教育、そして賞与に反映するのかについての議論をおこなわなければなりません。賞与総額のどの割合を目標達成により変動させるのか、結果として総額に対しどれだけの差をつけていくのかといったことについても段階的な導入を検討し、スケジュール立案を行うことも大切です。通常は、目標達成の比率を2割から3割に設定するところが多いようです。
組織一律ではなく部署や個人の業績を目当てに評価を行います。業績は目標が達成できたかどうかを基礎とするため、
- 目標管理制度における「評価」の質的向上
- そのための評価者訓練の継続的実施
- 発見事項に対する恒常的な教育体制の整備
- 賞与のどれほどの割合を評価の対象とするのかの決定(例:80%は固定、20%について差をつける)
- 目標管理制度による評価を活用した賞与支給
といった活動が必要です。
人事考課においては、少なくとも、
- 情意考課のための情意考課表
- 能力考課のための職務基準やその詳細を説明したマニュアル、チェックシート等
- 日常活動の集計表
が作成されなければなりません。
上記をいつまでにどのように実行するのかを議論する必要があります。明確な目標を持ちスケジュール立案を行い、導入までのおおよその期日を決定しなければ、なかなかうまく作業が進みません。それぞれのプロセスにおいて必要な資料を整理したうえで、院内でWG(ワーキンググループ)を組成するなどの活動が必要となります。早急に全体像を把握し、どのように作業を行っていくのかについてのスケジュール管理を行わなければなりません。
なお、これらは本来処遇のために行うべきものではありますが、前述したように同時に教育の基礎でもあります。間違いなくいえることは、人は評価されて動くということです。無関心のなかでは人は動かないし成長できません。逆に積極的に動いている人が、無関心という環境のなかでやる気を削がれているということに気が付く必要があります。無関心は、やる気のない人の格好の餌食であり、やる気のある人の墓場のようなものです。
人を多面的に評価し、成長機会を提供することこそが組織の役割であり上司の機能だということを忘れてはなりません。そうであるとすれば、組織的に評価の多角度的な実施を行う必要があり、そのための人事考課であり賞与の評価だ、と理解することが適当です。
多面的な評価を行える組織が、多面的に人を育成し、成果をあげる組織であると私は思っています。とりわけ病院は労働集約的知的産業であり、であるとすれば人が医療の質を左右することは明らかです。医療崩壊が叫ばれる大変な時代であるからこそ、人材育成を図らなければなりません。
厳しい医療環境を迎えて、まずトップマネジメントが考え実践しなければならないことは、こうした多様な評価制度をつくり課題を発見し、教育につなげていくことであることを強く認識する必要があります。」