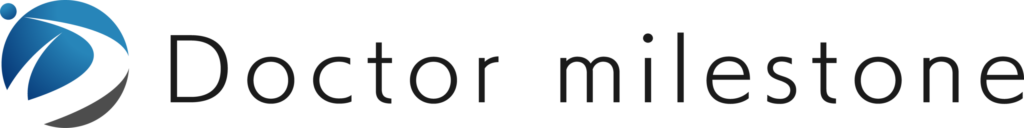ノウハウという言葉を語るときにナレッジマネジメントを考えます。頭に浮かぶのは野中郁次郎のSECIモデルです。SECIモデルは、個人が持つ知識や経験を集約して組織全体にノウハウを共有した上で、新たな知識を生み出すためのフレームワークをいいます。
暗黙知を形式知化に、個人知を組織知にというのは昔理解していた内容です。すなわち個人の持っているノウハウをマニュアルを使って形式知にすることにより、ある個人のノウハウが他の人にも見えてくる。そのノウハウを見た人は、ある行為について実際に体験していなくても疑似体験を行うことができ、全く何も知らない人よりも、うまく一定の行為を行うことができる。このプロセスを経て、個人の知識が組織の知識になります。
マニュアルにより得た知識をマニュアルを作成した人以外が学びノウハウを習得したうえで、さらに誰かが新しいノウハウを身に着け、それをマニュアルを通じて形式知化すると、個人の知識はさらに組織知になり広がります。暗黙知→形式知→暗黙知2→形式知2→暗黙知3→形式知3となり、どんどん組織や個人のノウハウ(ナレッジ)が進化していきます。
SECIモデルは、そのプロセスを自分でノウハウをつくる内面化、それを話し合いにて共同化する、そしてそれを形式知として表出化し、学習等により結合化する。それがさらに個人の中で内面化し、共同化、表出化、結合化といった繰り返しにより進化していくという流れを示しています。
無印良品が業務改善やマニュアルによるナレッジマネジメントでV字回復したといわれますが、多くの企業がこれらの考え方により仕事の質を高め、個人の成長を図り、業容の拡大を得ています。
私も長い間業務改善活動により、簡素化、移管、内製化・外注化、廃止そして何よりも標準化を図りながらマニュアルを活用して組織改革を行うながれをつくる仕事をしていましたが、まさにマニュアル項目を列挙→マニュアル作成→ノウハウ抽出→学習→業務改善→マニュアル改定→学習→業務改善というながれのなかでSECIモデルを体現しようとしていました。当時マニュアルを紙媒体で管理していたころからすれば、いまはさまざまなシステムやデバイスがありナレッジマネジメントはとてもやりやすくなっています。
過去、卸売業、流通業、製造業、建設業、飲食業、医療、介護でこの考え方をベースに改善を行ってきました。しかし、これらの業種にある作業自体はベンチマークできることが数多くあり、流通業の販売政策や、物品管理は医療においても有効ですし、建設業の工程管理や製造業の原価計算(個別原価計算や工程別原価計算、特殊原価調査)も医療や飲食等でも活用することができます。医療の接遇は、笑顔挨拶礼節ではなく、痛みを与えない、羞恥心を与えない、恐怖心を与えない、納得してもらう、不快な思いを与えない、不利益を与えないと考えると、すべての業種で採用されるべき仕事の質そのものの到達点であり、同様の行為が必要だと分かります。
例えばパートの方々が清掃のナレッジを提供すれば、一つの清掃会社だけではなく多くの同業だけではなく、工事現場や工場でも役に立つし、どのような営業においてもある業種でのナレッジは他の業種においても使えます。物品管理でも、業務改善でも同様です。同業では言うに及ばず、業種、職種を問わず、そうしたナレッジを開示し共有できる場があれば、大きな価値を生むし仕事の質を高め、個人を成長させ、生産性を高めることができます。
つまらないことと考える向きもあるかもしれませんが、多くの組織や個人で活用されるナレッジやノウハウを徹底的に開示し、提供し合い、社会全体でSECIモデルのフレームワークが活用できるシステムが構築されるとどんなに素晴らしいかと、ふと思い、なぐり書きをしてみました。
先ずは自分から始めるとして、目を皿のようにして、
- 世の中でどのようなやり方があるのか情報収集し把握する
- その本質はなんなのかを考える
- 何が特徴なのかを想定する
- どう活用できるのかを回りにいる信頼できる人と話し合う
- ロジックを見極める
- スマートフォンに記録する
- 実際に使ってみる
というながれをつくりあげ、自分の血肉にしていけるよう行動し、いずれは小さなノウハウであっても多くの人が共有でき仕組みをつくっていきたいと考えています。