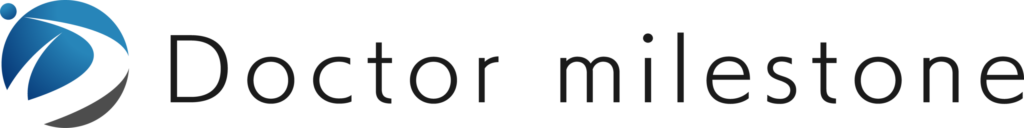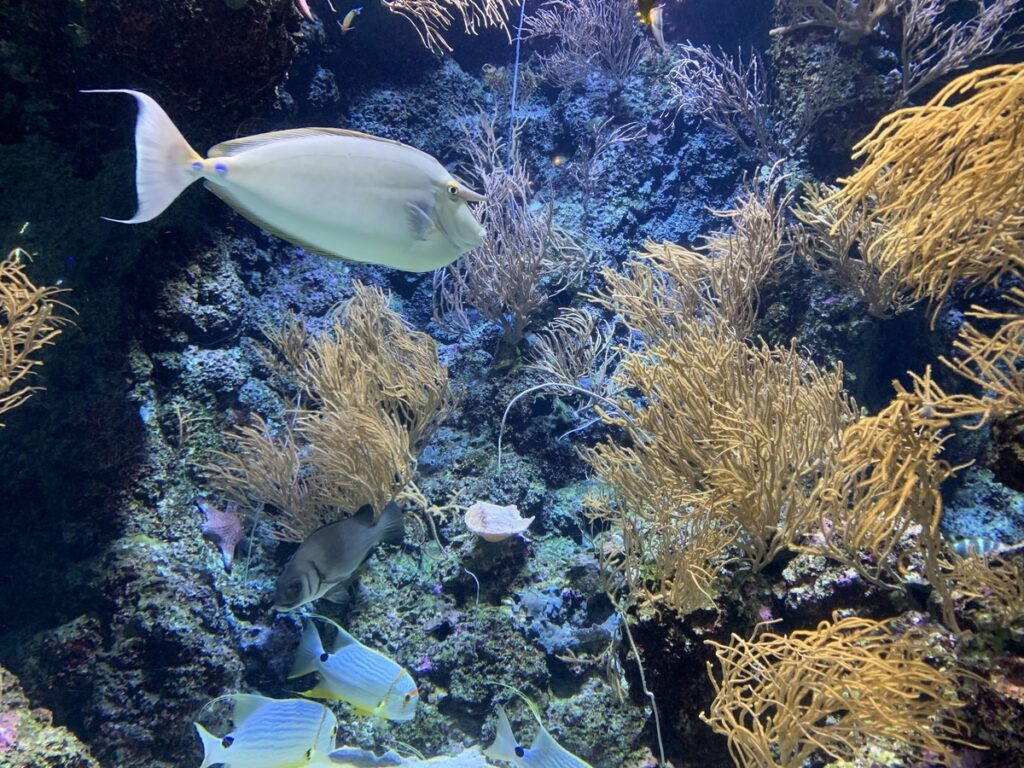
組織においては、コミュニケーションすなわち、ヒトの間で行われる感情や思考の伝達がとても大切です。コミュニケーションが仕事の軸になるからです。コミュニケーションが活発に行われる組織では、1+1以上の成果を挙げることができます。
少なくとも、
- 連携により円滑に事が進む
- ある業務を相互に補完し合える
- 何かあったときに支援し合える
- 他者から啓発される、学べる機会を持てる
- 一人ではないという意識が自分を鼓舞する
と言った効果が考えられます。
仕事において、これらの振り子が逆に振れると大変なことになります。
- じゃまする、
- 協力できない、
- 助け合えない、
- けなし合う、
- 排除する
などの行為は明らかに生産性を阻害します。
ヒトが重要な資源である医療機関では、明らかにコミュニケーションの良し悪しで、成果が大きく異なります。職員が、たった数人しかいない診療所でも、コミュニケーションがうまくいかず、職場がギクシャクし、生産性が落ちてしまうことがあります。人間関係が悪くなると物事が進まないのは明らかです。院内コミュニケーションをどのようにとればよいのかを考えてみる必要があります。
なくてはならない事項は次のものです。
- 組織のビジョンが明確である
- 具体的な実行スケジュールが決定されている
- 各職員の役割が明確である
- 組織トップが常にものごとに執着し、うまくいくよう気配りをしている
- 職員一人ひとりの業務が、計画通りに進んでいるのかがチェックされている
- うまくいかない理由があれば、組織全体でそれを支援し、修正している
- 成果をあげる職員を評価する
- 成果をあげていない職員を教育する
- 何よりも職員が相互に信頼し合っている
これらが一つでも欠けると、本来のコミュニケーションを円滑に行うことが難しくなります(なお、ここでのコミュニケーションは社会的活動を前提としており、単に仲が良いということだけを対象としているのではありません)。
仕組みがなくても、コミュニケーションができている組織は、特定の職員がリーダーとして高い意識をもち、コミュニケーションをとれるよう行動し、結果を出しています。ほんの数人が業務を円滑に行うため、まとまることで、組織が成果をあげているのです。しかし、リーダー頼りのマネジメントは長続きしません。リーダーシップをとっている者が異動したり退職すれば、コミュニケーションは悪くなる可能性があるからです。仕組みがなければなりません。
中期経営計画立案、目標管理制度やBSC(バランストスコアカード)による年度目標の管理、指標管理や管理会計による現状の可視化、さらには業務マニュアルの運用や業務改善提案、教育システム、評価制度が整備されていることで目的を達成します。
完全でなくてもよいのですが、小さい組織であったとしても、上記を整備していこうという方向や具体的な指示が必要です。徐々に、共通の目標が自院や各部署のコミュニケーションを活発化し、職員の覚醒を促すからです。
なお、職員間の関係性を改善するために、組織で一体となった行動がとれるよう、地域イベントやボランティア、そしてときには飲み会などを行うことも有効です。私は、飲み会でのコミュニケーションは無駄と思っていて、自分は好きではありませんでしたが、メリハリの効いた機会に食事をすることは必要かな、と思っています。ただ、基本は組織内の仕組みづくりが徹底して行われなければなりません。
この部分を忘れることなく、院内コミュニケーションを活性化し、各職員や各部署の機能が最大限発揮できるよう、リーダーの日々の活動が望まれます。我が身に置き換えると難しい事ですが、あるべき形にできるだけ早くしていきたいと、私は小さな決意をしています。