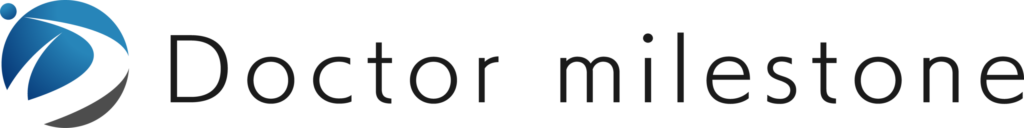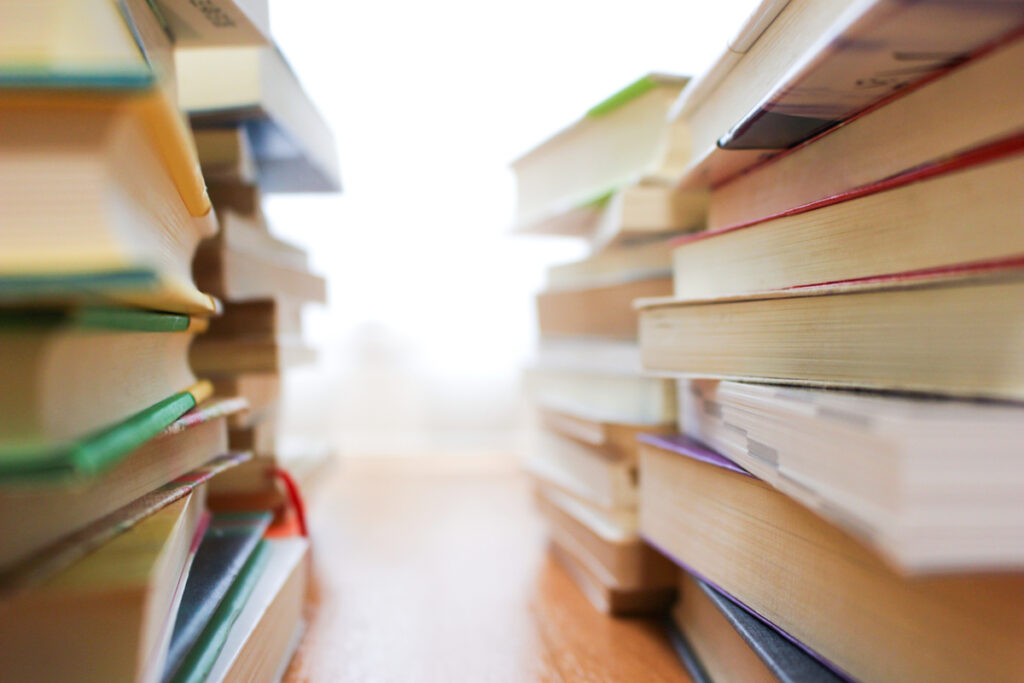
仕事において「自分が何をやりたいのか、よくわからない」、という人は意外と少ないと思います。何が好きなのか、何な興味があるのかを胸に手を当てて考えればすぐに答えを出すことができます。今できているかどうかは別として漠然としてでも、また曖昧でも、何かがそこにあるのではないかと考えているのです。
もし、そこに何もないのであれば、早急にそれを探していかなければなりません。やりたいことがなくても、十分に幸せだという人は、それでもいいと思います。でも、やりたいことができたときの、この上ない喜びや達成感を味わいたいのであれば、血眼になって忘れ物を捜しに行く必要があるかもしれません。場合によれば、やりたいことそのものだけではなく、自分の気持ちや情熱など、それを生めない自分自身の現状を振り返ることも大切ですね。
なお、仕事には、やりたいことだけではなく、やらなければならないことがあります。やらなければならないことは、好きか嫌いか興味の有無にかかわらず、やらなければならないこと、他からの要請に基づいて、また見るに見かねて、やらなければならないこと、の二つがあると思います。
やりたいことのへ思いが強く、これは私の使命だと、やりたいことを、やらなければならないことにまで引き上げていくことがあります。その思いをもてば力が出るし成果もあがりますね。
そうはいっても、そうした思いをもって、やりたいことを仕事にできる人はそれほど多くはないないかもしれません。
本当にやりたいことは、なかなか仕事にしていくことはできないけれど、仕事で、どうしてもやらなければならないことから、やりたいことを見つけ、自分のやりたいことに擦り合わせながら力を身に着けていくことが正解なのかもしれません。そうして仕事を充実させている人はやはり幸せです。
私たちは一人で生きているのではありません。何等かの社会や地域、組織に属して活きています。やらなければならないことのなかには、やりたくないこともあります。やりたいことだけをして、やりたくないことをしません、というのでは仕事はできませんし、組織やから受容れられません。
嫌なことであっても興味がないことであっても、何かのために何かをしなければならないことがあるのです。自分のためだけに、やりたくないことをし続けるのは苦しいとしても、誰かのために何かをすることが本来もってうまれた人としての役割だと考えています。
誰かのために何かをするなかで、相手のことを思い、考え、また組織のことを思い、考え、そして徐々に相手や組織の立場に立ってものごとを考えることができるようになります。
いきなり、やりたくないけど、誰かのために仕事をしていこうと気負うのは荷が重すぎます。やらなければならないことから、やりたいことを見つけ、力をつけていくとともに、やりたくないことも含め、やらなければならないことを整理し、納得して仕事に取り掛かり、それらをクリヤーしていくことが必要です。そのことで、さまざまなことに触れ、積極的にそれを受け入れ取り組んで成果を挙げていく。その成果があれば、感謝されるし、自信もつきます。
ここで書いたことは当たり前のことのようではありますが、私も含め、なかなか納得して何かをするということに慣れていない人も多いのだと最近思います。何でもかんでも首を突っ込むということは時間のないので仕事に馴染まないし、緊急性や重要性、そして困難性に基づき優先順位をつけ、また取捨選択をするのはいたしかたないでしょう。しかし、他の何か、いやなことでもやらなければならないことの受け入れ態勢をつくっておけば、学ぶこともたくさんあるし、自他ともに役に立つことができるという結論です。
今日の話を整理すると、仕事の構造は次のようになります。
1.やりたいこと
2.やらなければならないこと
(1)他者の要請によりやる
①やりたいことを見つける②嫌なことでも積極的にやって役に立つ
(2)見るにみかねてやる
①やりたいことを見つける②嫌なことでも積極的にやって役に立つ
(3)やりたいことを高める
やりたいことをできる自分をつくることや、やらなければならないことのなかでやりたいことを見つけて仕事をする。同時にやりたくないけど、やらなければならないことについても、前向きに捉え、成長の肥やしにする、といったことを大切にして、日々の仕事に挑戦していきたいものです。